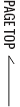東日本大震災・復興への第一歩 被災地に二輪車を活かす
本ページは、一般社団法人日本自動車工業会が発行している月刊誌「Motorcycle Information」2011年05月号の記事を掲載しております。
東日本大震災の発生後に、本誌記者は宮城県の仙台市と気仙沼市を取材した。大災害の現場を二輪車で見て回り、二輪車販売店や二輪車ユーザーの声を聞いた。仙台市の早坂サイクル商会では、「地域が早く元気になるように貢献したい」と、震災翌日から来客に応対した。津波の被害が大きかった気仙沼市の販売店でも、早々に2店舗が店を開いていた。モトショップヒロノの廣野さんは、90ccの二輪車で津波から母親を救った。Motor's Shop EBINAでは、常連客がショップに集まり安否情報を交換するなど、情報スポットの役割も担った。

想像を絶する津波の被害(気仙沼市)
阪神・淡路大震災(1995年1月)では、道路が寸断されて大渋滞が発生し、小回りの利く二輪車が注目された。二輪車は、被災者の生活の足として役立ったばかりでなく、緊急救援活動や被災地支援のボランティアにも活用され、復興の支えとなった。
今年3月11日に起きた東日本大震災は、阪神・淡路大震災の180倍もの地震エネルギーによって引き起こされ、とくに東北地方の太平洋岸には大津波が押し寄せ、沿岸の市や町は壊滅的な被害を受けた。
本誌記者は、3月28日に宮城県の仙台市と気仙沼市に入り、4月1日まで取材を行った。そのとき二輪車はどのように使われたか――。現地の声に耳を傾け、これからの復興に二輪車がどのように役立つか考えたい。
二輪車で大津波の被災地へ

再開した東北自動車道(国見P.A./3月28日)
震災後、東北地方の最低気温は氷点下の日が続き、季節はずれの降雪もあった。そうしたなか3月24日に、東北自動車道は全線にわたって通行規制が解除された。寒さもだんだん和らぐ見通しになり、本誌記者は28日、東京から二輪車で宮城県の被災地へと向かった。大災害の現場を見て回り、二輪車販売店や二輪車ユーザーの声を聞くのが目的だ。
再開したばかりの東北自動車道は、家族の安否を気遣う一般車両をはじめ、自衛隊や消防などの救援車両も多かったが、滞りもなく順調に流れていた。震災直後から街のガソリンスタンドは大半が閉まっており、"ガス欠"の不安もあったが、高速道路のサービスエリアでは、並んでも30分足らずで給油することができ、燃料の手当ては確実に進んでいる印象を受けた。
また、地震の影響で、路面には少し段差のある場所もあったが、とくに交通事故も発生しておらず、何事もなく仙台に到着することができた。災害発生から2週間で、東北の大動脈はほぼ完全に機能を取り戻していた。
二輪車だからこそできた早業――早坂サイクル商会

客足が途絶えない早坂サイクル本店

早坂理さん
仙台市内に入ると、営業しているガソリンスタンドにはクルマが並び、長蛇の列をなしていた。街なかでの給油はまだ困難な様子。市民生活も不自由で、電気と電話の復旧は進んでいたが、水道とガスは途絶えたまま。下水道にも支障がある区域が多く、飲料水の確保、炊事、風呂、トイレなど、たいへんな不便が続いていた。
市内に10店舗を構える「早坂サイクル商会」は、自転車から大型二輪車までを取り扱う老舗の二輪車販売店。県庁近くにある本店を訪ねてみると、すでに通常営業を始めており、ひっきりなしに来店する客に、スタッフが手際よく応対していた。
常務取締役の早坂理さんは、大地震のあった3月11日の様子を次のように話す。「わたしたちは日ごろから地震を警戒して、陳列する商品の固定には細心の注意を払っているんですが、それにもかかわらずほとんどのバイクがなぎ倒されました。ものすごい揺れで、あれではどうしようもなかった」と首をすくめる。
早坂さんは、一緒にいたスタッフの無事を見届けると、ほかの店舗に電話が通じなかったため、ただちに二輪車で出かけた。その日のうちに市内すべての店舗を見回り、それぞれの店長やスタッフを励まして、今後の対策に当たったという。街は停電のために信号が止まってクルマは大渋滞を起こしていた。二輪車だからこそできた早業だった。
「こういうときにバイクの機動力は本当に頼もしい。店を回ってみると、気持ちが動転して泣き崩れている女性スタッフもいましたから、その日はすぐに店を閉め、帰宅できる人には帰ってもらいましたが、二次災害を避けるために、店の片づけができる人には残ってもらい、『気持ちをしっかり持って、やるべきことをやろう』と、声をかけあいました」という。夜が更けてきて、停電で真っ暗ななか、季節はずれの大雪があたりを真っ白にしていくのが異様に見え、早坂さんは「これも大地震のせいか?」と、ふと怖さを感じたと振り返る。
地域が早く元気になるように

久松茂雄さん
早坂さんのショップには、翌日から「この自転車がほしい」「すぐに乗れる原付はない?」という客が次々にやってきた。仕事で仙台に来ていた近隣の塩釜市や石巻市などの人たちが、自宅まで帰る手段がなくなって困り、自転車か原付を買って家まで乗って帰りたいということだった。ほかにも、自宅の車庫にしまってあった二輪車を持ってきて、「乗れるように整備してほしい」というケースが急に増えた。
「私たち店のスタッフも、多かれ少なかれみんな地震の被災者なんです。でも、『早く家族に会いたい』『わが家に帰りたい』という人たちが喜ぶのを見ると、店を閉めておくわけにはいかない。家が流されてまだ出勤できないスタッフもいますが、地域が早く元通り元気になるように、仕事をやれる者はやれる限りやって、頑張るしかありません」と、早坂さんは話している。
ちょうど原付とヘルメットを購入しにきた男性に話を聞いた。市内に住む会社員の久松茂雄さん(55歳)。久松さんは、「先週から会社の仕事が始まったんだけど、ガソリン不足が深刻でクルマが自由に使えないんですよ。せめて燃費のいい原付で動き回ろうと、三十数年ぶりでバイクに復帰です。今回の災害の大きさを考えれば、仕事ができるだけでもありがたい。バイクでバリバリ働きますよ」と微笑んだ。
津波によって深刻な被害を受けた気仙沼

家が粉砕されて一面のがれきとなっている

津波のあと炎上した一帯
記者はこの日の夜、津波で街の中心部が壊滅した気仙沼市に入った。取材は翌朝から開始し、二輪車で市街地を走ってみると、市内を南北に通る国道45号から海岸までの被害がとくにひどい。道路の脇にはがれきの山。粉々になった家の残骸が広範囲に堆積し、その先に海が見える。家があったはずの場所で、何かを探している人たちの姿もある。火災が発生した町では、焼けたがれきの上に巨船が乗り上げていた。想像を絶する津波の猛威に、固唾を呑んで立ち尽くすばかりだった。
一度水没した街の中心部では、営業している商店はまったく見当たらない。街はずれまで移動すると、停電や断水の不自由さにもめげず時間限定で開いているスーパーマーケットがかろうじて1軒、ほかにも開いている店はもう2軒、目に留まった。「モトショップヒロノ」と「Motor's Shop EBINA」の両店で、いずれも津波を免れた二輪車販売店だった。
この二輪車は"命の恩人"です――モトショップヒロノ

モトショップヒロノ(新店舗)

旧店鋪があった方角を指す廣野さん
「モトショップヒロノ」は、市の中心部に創業50年の旧店舗と、そこから3kmほど離れた国道45号のバイパス沿いには、7年前に開いた新店舗がある。社長の廣野武男さんは新店舗に常駐し、旧店舗のほうは廣野さんの母親が切り盛りしていた。しかし、3月11日の大津波で、その旧店舗は失われてしまう。
廣野さんは、大地震が起きてすぐ、広域拡声器で大津波警報が発令されると、母親と旧店舗を心配して、軽トラックで新店舗を飛び出した。
「ところが、街の中心部に向かう主要な道は、信号が止まってすぐに渋滞が始まったんです。これはダメだと思い、いったん店に引き返し、いつも足にしている90ccのビジネスバイクに乗り換えて母のところに向かったんです」と、廣野さん。
大きな橋を渡って市街地に入ると、廣野さんは幸運にも避難のために移動している最中の母親を見つけ、二輪車の後ろに乗せると、とにかく無我夢中で高台を目指して走った。
「間一髪でした。高台から見ていた知人は、私のバイクが通ったすぐ後に津波がきたんだと教えてくれました。私にとってこのバイクは、本当に"命の恩人"です」
被災地で求められた二輪車の利便性
津波から数日間、街には着の身着のままで行きかう人たちが増えた。避難所で夜を過ごしながら、行方がわからなくなった家族を探したり、自宅に徒歩で帰ろうという人たちが国道沿いに大勢移動していた。
「泥水につかってヘトヘトに疲れてる人が店にやってきて、『家族が心配だから自宅まで帰りたい。バイクを貸してほしい』と言うんです。聞けば自宅までまだ30kmもある。私は、『これで早く家族に会ってあげなさい』と、仕事で使っているバイクを渡しました。同じような人が何人もやってきたので、動く車両を次々に貸し出して、もう誰に渡したかもわからない」と、廣野さんはいう。店を開けているのは"営業"というよりも、職業的な使命感だった。
とくにパンクの修理依頼が増えた。がれきのなかを走るため、ガラスや釘がタイヤに刺さってしまう。故障している二輪車だと、部品の調達が困難なため、どうしても修理には時間がかかる。20台ほど在庫していた原付は、すぐに売り切れてしまった。
「津波で家もクルマも流されて、親戚の家に世話になってるから、せめて水や食料などの確保を手伝うのに"足がほしい"という人が多数。家族の行方がわからないので捜索に使いたいという人や、会社がなくなって電話も通じないため、従業員の安否を確かめたり、取引先と連絡を取るのにバイクがほしいという人たちも少なくなかったですね」
気仙沼市には、被災から3日目に、5,000人規模の自衛隊員が到着して、一気に主要道路のがれきを撤去して、一定の交通環境を確保した。これによって、役所に行って手続きをしたり、病院に通ったり、安否情報を求めて避難所を回ったりなど、いろいろな市民の動きが出始めた。また、そうした行動が活発になるにしたがって、市内の交通渋滞が始まった。
廣野さんは、「こういう地方都市では、クルマがないと生活していけません。でも、今回の被災をきっかけに、バイクの便利さを改めて見直した人たちは多いはずです。その人たちには、常備薬のようにいつもそばに1台備えて、いざというときの機動力として使えるようにしておいてほしいものです」と話している。
地域が早く元気になるように

EBINAのスタッフ(中央がえび名さん)
「あとで分かったんですが、店の100メートル手前まで津波が来てました。ギリギリで助かってホッとしたり、ゾッとしたり」と話すのは、えび名 勝さん。2人の従業員と、国道45号のバイパス沿いで「Motor's Shop EBINA」を開いている。地震が起きたときは、揺れが激しくなり、店にいた客を外に誘導したところで、展示していた車両が次々に倒れた。拡声器で大津波警報が出たため、屋外の展示スペースに商品を残したまま、後ろ髪を引かれる思いで高台に避難したという。
「私も含めてスタッフの家族もみな無事だったので、翌日は閉店ということにして、店内の片づけや商品の点検に取りかかったんです。そうしたら、常連のお客さんが心配して様子を見に来てくれる。『店やってんだ、良かったね無事で』って。それも1人2人ではなくて、知ってるお客さんが次々に訪れて、声をかけてくださるんです」
そうしているうちにえび名さんの店は、二輪車仲間の安否確認の中心スポットになり、誰かの無事を尋ねるメッセージや、自らの無事を伝えるメッセージを店内に貼り出し、まるで被災情報センターのようになった。
「バイクショップってこんなに社会性がある場所なのかと、私自身、考えたことがなかった。店を閉めておくわけにはいかないということになって、あとはずっとフル回転のまま、まったく休んでいない状態です」と、えび名さん。パンクの修理、エンジンオイルなど消耗品の購入など、次々にやってくる客に、「お店が開いてて助かりました」と言われると、疲れも吹き飛ぶとのことだ。
仕事はバイクで十分できる

二輪車を購入した本山さん
気仙沼市内で設備会社の会長を務めている本山裕次郎さん(80歳)は、会社と自宅が津波で浸水。所有する四輪車の業務用と自家用車あわせて5台が水没して使えなくなった。落ち込んでいる社員を前に、本山さんはさっそく原付を1台購入してきて檄を飛ばした。「仕事はバイクで十分できる。バイクで得意先を回りゃいいじゃないか。山になったがれきを見ると『負けるもんか』とやる気が出る。少々金がかかったっていいから、さっさと片付けてしまわなくちゃ何も始まらないだろう」と。
本山さんは、子供のころ旧満州から引き揚げてきて、仕事一筋で身を立ててきた。若い時の経験を振り返って、「よし、昔と同じように、今こそバイクを手に入れて、動き回ってやろう」と、思い立った。40年以上前、本山さんは250ccの二輪車でテレビの販売営業をしていたことがある。「だから私は、自動二輪の運転免許もあるし、本当は原付じゃ物足りないんだよ。大型がほしかったが、あいにく売ってなかった」と苦笑い。
「八十のジイさんがバイクに乗って仕事を始めたんだから、若い人たちはこんな災害なんかに絶対に負けちゃダメだ。必ず復興できる。頑張ろう!」と、力強く呼びかけていた。
"小さいバイク"を復興のツールに

避難所にチョコレートを届けた
さて、今回の震災で、二輪車業界では、3月下旬に予定していた大阪モーターサイクルショーと東京モーターサイクルショーの開催を中止した。一般社団法人日本自動車工業会では、当日会場で配る予定だったチョコレート1,000個が手つかずのまま残ったので、支援物資として被災地に届けることにした。
記者はその役を引き受け、気仙沼郵便局留めで届いていたチョコレートを二輪車でピックアップし、市内の避難所3カ所に運び届けた。
どの避難所でも、子供たちが何人かグループで遊んでおり、チョコレートを差し出すと、はにかんだ表情で受け取ってくれた。避難所の担当者は、「お年寄りも若い人も、ちょうど甘いものがほしくなってきた時期だったので、うれしい」とのこと。
また、避難所にいた年配の男性は、「東京からバイクで来たの? そうやって遠くから支援に来てくれて本当にありがたい。避難所から出て歩きたくても、なかなかその気にならないし、小さいバイクなら私らにもいいかもしれんなあ」と話した。
被災者の気持ちが前向きになり、積極的に行動範囲を広げようという意欲が沸いてきたとき、排気量の小さい手軽な二輪車は、復興の大事なツールになりそうだ。
災害時において、コンパクトで機動力のある二輪車は、ときに人命にもかかわる働きをする。がれきのなかを、「どうしても移動したい」というニーズに応えて、いちばん苦しいときに人と人との大切なコミュニケーションを支えていた。
記者の訪ねた被災地では、少しずつ生活環境が復旧し、交通の主流はクルマに戻りつつあった。そして二輪車は、渋滞に左右されない効率的な移動手段として、街に活気を呼ぼうとしていた。多くの人たちに身近に感じられる二輪車の手軽さ、機動性、経済性が、東日本の1日も早い復興に役立つよう強く願うものである。
本ページは、一般社団法人日本自動車工業会が発行している月刊誌「Motorcycle Information」2011年05月号の記事を掲載しております。